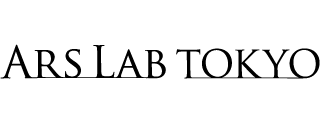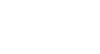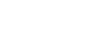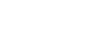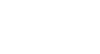ABOUT US
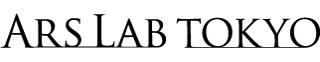
アルスラボ東京は
2024年秋、創設5周年を迎えます。
アルスラボ東京は東京都北区を中心に活動する「東京都一般吹奏楽連盟加盟」のアマチュア吹奏楽団です。令和元年(2019年)の楽団創設から今年の秋で“5周年”を迎えます。母体を持たず、吹奏楽愛好家が集って結成されたこの楽団はこれまで4回の自主公演を行いました。2022年度からは吹奏楽コンクールへの出場やアンサンブル、依頼演奏など年間通して様々な活動を行なっています。
PICK UP!!
団員募集について
2024.04.16
もうすぐ新年度スタート。
当楽団で新たな音楽活動をはじめましょう!
当楽団では入団希望のお申し込みを随時受け付けております。
私たちの仲間として一緒に演奏しませんか?この春からの新生活、進学などで楽団をお探しの方も、ぜひご検討ください。
皆さまのお申し込みお待ちしております。
VIEW MORE
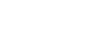
第3回定期演奏会終演のご挨拶
2024.01.07
ご来場ありがとうございました!

アルスラボ東京 第3回定期演奏会
サンパール荒川 大ホール
アルスラボ東京の創設5周年となる“2024年”の年明け、1月6日(土)サンパール荒川 大ホールに於いて定期演奏会を開催しました。 多くのお客様にご来場いただき、盛況のうちに幕をとじることができました。
これからもアルスラボ東京をよろしくお願いいたします。
VIEW MORE
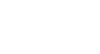

PAST ACTIVITIES